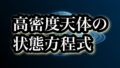目次
第1部:宇宙の晴れ上がりとは何か
第2部:バリオン-光子結合の物理(次回掲載予定)
第3部:宇宙マイクロ波背景放射と最終散乱面(次回掲載予定)
第1部:宇宙の晴れ上がりとは何か
宇宙史における決定的な瞬間
宇宙の歴史において、約138億年前のビッグバンから約38万年後に起こった出来事は、現代の宇宙物理学において極めて重要な意味を持ちます。この時期を「宇宙の晴れ上がり」あるいは「再結合期」と呼びます。この現象は、単なる宇宙史の一つのエピソードではなく、私たちが今日観測できる宇宙マイクロ波背景放射(CMB)の直接的な起源であり、宇宙の構造形成や物質の分布を理解する上で欠かすことのできない基礎的な物理過程なのです。
宇宙の晴れ上がりを理解するためには、まず初期宇宙の状態を把握する必要があります。ビッグバン直後の宇宙は、現在とは全く異なる極端な環境でした。温度は数十億度という途方もない高温状態にあり、密度も現在の宇宙の平均密度の何兆倍もの値でした。このような極限状態では、物質は原子として存在することができず、電子と原子核が完全に分離した「プラズマ状態」で存在していました。
このプラズマ状態の宇宙では、自由電子が至る所に存在しており、光子は電子と頻繁に衝突を繰り返していました。この現象を「トムソン散乱」と呼びます。トムソン散乱により、光子は宇宙空間を直進することができず、わずかな距離しか進むことができませんでした。現在の宇宙では光は何十億光年もの距離を自由に進むことができますが、当時の宇宙では光の平均自由行程は極めて短く、宇宙は完全に「不透明」な状態だったのです。
宇宙の膨張とともに、密度と温度は徐々に低下していきました。宇宙論的パラメータによると、宇宙の温度は時間の経過とともにスケール因子の逆数に比例して下がります。具体的には、温度Tと宇宙年齢tの関係は、T ∝ t^(-1/2)で表されます。この冷却過程が進むにつれて、ついに原子核と電子が結合して中性原子を形成することが可能な温度に達したのです。
プラズマ状態から透明な宇宙へ
再結合期における物理的変化を詳しく見ていきましょう。宇宙の温度が約3000ケルビンまで下がったとき、水素原子核(プロトン)と電子の結合エネルギーが熱エネルギーを上回るようになりました。水素原子の電離エネルギーは13.6電子ボルトです。これをケルビン温度に換算すると約15万8000ケルビンになりますが、実際の再結合は統計力学的な効果により、もっと低い温度で起こります。
再結合の過程は段階的に進行します。最初に、最も結合エネルギーの大きいヘリウムイオン(He²⁺)が電子と結合してHe⁺になります。これは宇宙の温度が約5000ケルビン程度の時期に起こります。次に、温度がさらに下がって約3000ケルビンになると、水素イオン(プロトン)と電子の結合が始まります。宇宙の物質の約75パーセントが水素であるため、水素の再結合は宇宙全体の透明度に決定的な影響を与えます。
この再結合過程において重要なのは、「サハの方程式」で記述される熱平衡状態の考慮です。サハの方程式は、温度と密度が与えられたときの電離度を計算する基本的な関係式です。この方程式によると、電子密度ne、プロトン密度np、中性水素原子密度nHの間には、温度Tと電離エネルギーχを用いて以下の関係が成り立ちます:
ne × np / nH = (2πmekT/h²)^(3/2) × exp(-χ/kT)
ここで、meは電子の質量、kはボルツマン定数、hはプランク定数です。この式から、温度の低下とともに中性原子の割合が急激に増加することがわかります。
実際の再結合過程は、単純な熱平衡よりも複雑です。宇宙の膨張による非平衡効果や、再結合時に放出される光子の影響も考慮する必要があります。水素原子が形成される際には、13.6電子ボルトのエネルギーが光子として放出されますが、この光子は別の水素原子を再び電離する可能性があります。しかし、宇宙の膨張により光子のエネルギーは赤方偏移によって減少し、また宇宙の密度も低下するため、最終的には再結合が優勢になります。
再結合期の基本メカニズム
再結合期の物理を理解するためには、複数の時間スケールを考慮する必要があります。まず、宇宙の膨張時間スケールがあります。これはハッブル時間と呼ばれ、その時代のハッブル定数の逆数で与えられます。再結合期では、この時間スケールは約10万年程度でした。
一方、原子過程の時間スケールは、宇宙の膨張時間よりもはるかに短いものです。水素原子の基底状態への遷移時間は、自然放出により決まり、約10億分の1秒程度です。しかし、励起状態から基底状態への直接遷移は禁制遷移であり、実際には準安定状態である2s状態を経由した二光子放出過程が重要になります。この過程の時間スケールは約0.12秒と比較的長く、宇宙の膨張を考慮した動的な解析が必要になります。
再結合過程における光子との相互作用も重要な要素です。プラズマ状態では、自由電子による光子の散乱(トムソン散乱)が支配的でした。トムソン散乱の断面積σTは、古典電子半径reを用いて、σT = (8π/3)re² ≈ 6.65 × 10⁻²⁵ cm²で表されます。この値は光子のエネルギーに依存しない定数であり、電子密度が高い限り光子の平均自由行程を短くします。
電子密度が十分に高い間は、光子の平均自由行程λは、λ = 1/(neσT)で与えられます。再結合前の宇宙では、電子密度は約200 cm⁻³程度であったため、光子の平均自由行程は約0.1パーセク(約3 × 10¹⁶ cm)程度でした。これは当時の宇宙の地平線距離と比較すると極めて短い距離であり、光子は完全に拡散的な運動をしていました。
再結合が進行すると、自由電子の数密度は急激に減少します。電子密度の減少率は再結合率に依存し、この過程は非線形的な特徴を持ちます。電離度xeを自由電子数と全電子数の比として定義すると、xe = ne/(ne + nH)となります。サハの方程式から予想される平衡値と比較して、実際の宇宙では膨張による非平衡効果により、再結合は若干遅れて進行します。
この非平衡効果を正確に計算するためには、詳細な原子過程を考慮した数値計算が必要です。現代の宇宙論計算では、「RECFAST」や「CosmoRec」といった精密な再結合コードが開発されており、観測されるCMBスペクトラムとの比較において重要な役割を果たしています。これらのコードでは、水素とヘリウムの多準位原子モデルを用い、各準位間の遷移率、コリジョナル過程、光子場との相互作用を詳細に計算します。
再結合期の終了時期は、通常「可視深度τ」という概念で特徴づけられます。可視深度は、現在から過去に向かって積分したトムソン散乱の光学的厚さを表します。τ = ∫₀ᵗ neσTc dt’で定義され、τ = 1となる時刻が「最終散乱面」と呼ばれます。この面は、現在観測されるCMB光子が最後に電子と散乱した時期に対応しており、宇宙の年齢約38万年、赤方偏移z ≈ 1090の時期になります。
最終散乱面の形成は段階的な過程です。可視深度τ = 10から τ = 0.1の範囲で大部分の散乱が起こり、この期間は「再結合の幅」と呼ばれます。赤方偏移で表すと、Δz ≈ 80程度の幅を持ちます。この有限の幅は、CMBの観測において重要な物理的意味を持ち、特に小角度スケールでの温度揺らぎの減衰効果(シルクダンピング)の理解に欠かせません。
再結合期は単に宇宙が透明になった時期というだけでなく、宇宙の物質と放射の力学的関係が根本的に変化した時期でもあります。再結合前は、バリオン(陽子・中性子)と光子が電子を介して強く結合しており、音波として伝播する密度揺らぎが形成されていました。再結合後は、この結合が解かれ、バリオンは重力の影響下で自由に運動できるようになり、現在観測される大規模構造の形成が本格的に始まったのです。
第2部:バリオン-光子結合の物理
電磁相互作用と宇宙の不透明性
宇宙初期におけるバリオンと光子の強い結合は、電磁相互作用の基本原理に基づいています。この結合状態を理解することは、なぜ初期宇宙が不透明であったのか、そして再結合期にどのようにしてこの結合が解かれたのかを理解する上で極めて重要です。
プラズマ状態の宇宙では、物質は主に以下の構成要素で成り立っていました:
- 自由電子: 原子核から完全に分離した状態
- イオン: 主に水素イオン(プロトン)とヘリウムイオン
- 光子: 高エネルギーの電磁波
- 暗黒物質: 電磁相互作用をしない未知の物質
この中で、光子と直接相互作用するのは電荷を持つ粒子、つまり電子とイオンです。しかし、電子の質量がプロトンの約1836分の1と軽いため、光子との散乱は主に電子によって支配されます。
電磁相互作用の強さは微細構造定数α ≈ 1/137によって特徴づけられます。この値は自然界の基本定数の一つであり、光子と荷電粒子の相互作用の強さを決定します。初期宇宙の高温・高密度環境では、この相互作用が極めて頻繁に起こり、光子は電子との衝突により常にエネルギーと運動量を交換していました。
バリオンと光子の結合状態では、両者は熱平衡状態にありました。これは、光子と電子の衝突頻度が宇宙の膨張率よりもはるかに高かったためです。衝突頻度Γは、電子密度ne、光速c、トムソン散乱断面積σTを用いて、Γ = neσTcで表されます。一方、宇宙の膨張率はハッブル定数Hで表されるため、Γ >> Hの条件が満たされている限り、熱平衡が維持されます。
この熱平衡状態において、光子の分布は完全な黒体放射スペクトラムを示していました。温度Tの黒体放射におけるエネルギー密度分布は、プランク分布として知られています:
u(ν) = (8πhν³/c³) × 1/(exp(hν/kT) – 1)
ここで、νは光子の振動数、hはプランク定数、kはボルツマン定数です。この分布形状は、光子と物質の完全な熱平衡を反映しており、現在観測されるCMBの黒体スペクトラムの起源となっています。
トムソン散乱と光子の拡散
トムソン散乱は、光子と自由電子の弾性散乱過程であり、再結合期以前の宇宙における光子の運動を支配する基本的な物理過程でした。この散乱過程の詳細な理解は、最終散乱面の物理を把握する上で不可欠です。
トムソン散乱の特徴的な性質は以下の通りです:
- 断面積: σT = (8π/3)re² ≈ 6.65 × 10⁻²⁵ cm²(古典電子半径reに基づく)
- 角度依存性: 散乱強度は(1 + cos²θ)に比例(θは散乱角)
- 偏光: 散乱光は部分的に偏光する
- エネルギー依存性: 光子エネルギーが電子の静止エネルギーよりも十分小さい限り断面積は一定
散乱過程において、光子は電子との衝突により運動方向を変えます。この過程は確率論的であり、光子は「ランダムウォーク」と呼ばれる拡散運動を行います。光子が一定の距離を直進するのに要する時間は、散乱による遅延により著しく長くなります。
光子の拡散係数Dは、光速c、散乱頻度Γ、および散乱の等方性を考慮して、D = c²/(3Γ)で表されます。この拡散過程により、光子が距離Lを移動するのに必要な時間tdiffは、tdiff = L²/(3D) = (L²Γ)/(3c²)となります。これは直進時間tstraight = L/cと比較して、(Γ/c) × (L/3)倍も長くなります。
再結合前の宇宙では、電子密度が高いため散乱頻度Γが非常に大きく、光子の平均自由行程λ = c/Γは宇宙の地平線距離よりもはるかに短い値でした。具体的な数値を見ると:
- 再結合前の電子密度: ne ≈ 200 cm⁻³
- 散乱頻度: Γ ≈ 4 × 10¹⁶ s⁻¹
- 平均自由行程: λ ≈ 7 × 10⁻⁶ cm(当時のスケール)
- 地平線距離: dH ≈ 10⁵ パーセク
この比較から、光子が宇宙の地平線距離を移動するには、直進の場合の約10¹⁵倍の時間が必要だったことがわかります。
結合解除の臨界条件
バリオン-光子結合の解除は、段階的かつ非線形的な過程です。この過程を定量的に理解するためには、複数の物理的条件を同時に考慮する必要があります。
結合解除の主要な判定基準は以下の通りです:
- 散乱頻度条件: Γ < H(散乱頻度が宇宙膨張率を下回る)
- 平均自由行程条件: λ > dH(光子の平均自由行程が地平線距離を超える)
- 結合時間条件: tcoupling > texpansion(結合時間が膨張時間を上回る)
これらの条件は相互に関連しており、電子密度の減少とともに同時に満たされるようになります。
電子密度の時間発展は、宇宙膨張による希釈効果と再結合による減少効果の組み合わせで決まります。宇宙膨張による密度の希釈は、ne(t) ∝ (1+z)³の関係に従います。一方、再結合による電子密度の減少は、電離度xe(z)の時間発展により記述されます。
電離度の発展方程式は、詳細なバランス方程式として表されます:
dxe/dt = αH(T)[nH(1-xe) – neβH(T)xe] – 3Hxe
ここで、αH(T)は水素の再結合係数、βH(T)は電離係数、nHは水素原子核密度です。この方程式の解は、温度の関数として急激に変化し、臨界温度付近で電離度が1から0.1程度まで急速に減少します。
結合解除過程における重要な時間スケールは「結合時間」tcouplingです。これは、バリオンと光子が熱平衡を維持するために必要な特徴的時間で、tcoupling ≈ 1/Γで与えられます。宇宙膨張時間texpansion ≈ 1/Hと比較して、tcoupling >> texpansionの間は強い結合状態が維持されますが、再結合の進行によりtcoupling ≈ texpansionとなる時点で結合解除が始まります。
結合解除の過程は、宇宙論的摂動の発展にも重要な影響を与えます。結合状態では、バリオンと光子は一体となって音波振動を行いますが、結合解除後はバリオンが重力崩壊を自由に起こせるようになります。この変化は「ジーンズ不安定性」の変化として現れ、構造形成の開始時期を決定します。
結合解除時期の宇宙論的パラメータを具体的に見ると:
- 赤方偏移: z ≈ 1090
- 温度: T ≈ 2970 K
- 電離度: xe ≈ 0.12
- 宇宙年齢: t ≈ 380,000年
- 密度パラメータ: Ωm ≈ 1(物質優勢期)
これらの値は、現代の精密宇宙論観測により高い精度で決定されており、標準宇宙モデル(ΛCDM模型)の基本パラメータと整合性が確認されています。
結合解除過程の理解は、CMBの詳細な観測との比較において極めて重要です。特に、偏光観測や小角度スケールでの温度揺らぎ測定では、結合解除の物理過程を正確にモデル化することが、宇宙論パラメータの精密決定に直結します。現在進行中の観測プロジェクトでは、結合解除過程のより詳細な物理、例えば禁制線遷移や三体再結合過程の効果まで考慮した高精度計算が求められており、理論と観測の両面からさらなる発展が期待されています。
第3部:宇宙マイクロ波背景放射と最終散乱面
CMB温度揺らぎの起源
宇宙マイクロ波背景放射の温度揺らぎは、現在観測される宇宙の大規模構造の種となった原始密度揺らぎの直接的な痕跡です。これらの揺らぎは、インフレーション期に生成された量子揺らぎが、宇宙の膨張とともに古典的なスケールまで引き伸ばされたものと考えられています。
最終散乱面における温度揺らぎの振幅は、平均温度に対して約10⁻⁵という極めて小さな値です。この微細な揺らぎが、現在の銀河や銀河団といった巨大な構造の起源となったという事実は、宇宙論における最も驚くべき発見の一つです。温度揺らぎΔT/Tの典型的な値は:
- 大角度スケール: ΔT/T ≈ 2 × 10⁻⁵
- 中間角度スケール: ΔT/T ≈ 6 × 10⁻⁵
- 小角度スケール: ΔT/T ≈ 3 × 10⁻⁵
これらの揺らぎは、最終散乱面上の異なる物理過程を反映しています。大角度スケールの揺らぎは主に重力ポテンシャルの違いによるものであり、これを「ザックス・ヴォルフ効果」と呼びます。中間スケールでは、バリオン-光子プラズマの音波振動が支配的となり、特徴的な振動パターンを生み出します。
音波振動の物理的メカニズムは、結合したバリオン-光子流体の状態方程式により決定されます。この流体の音速vsは、vs = c/√3(1 + R)で与えられます。ここで、Rはバリオンと光子のエネルギー密度比R = 3ρb/(4ργ)です。再結合期では、R ≈ 0.6程度の値を持ち、音速は光速の約55パーセント程度になります。
音波振動により形成される特徴的なスケールは「音の地平線」で決まります。これは、音波が最終散乱面までに伝播できる最大距離であり、現在の共動距離で約2度の角度スケールに対応します。このスケールは、CMBの角度パワースペクトラムにおける第一音響ピークの位置として観測されます。
最終散乱面の観測的意義
最終散乱面は、現在から観測可能な宇宙の最も遠い「表面」として、宇宙論研究において極めて重要な役割を果たしています。この面から放射される光子は、約138億年の時間をかけて現在の地球に到達し、宇宙創生期の物理的条件を直接伝える貴重な情報源となっています。
最終散乱面の観測により得られる主要な物理情報は以下の通りです:
- 宇宙論パラメータ: ハッブル定数、物質密度、暗黒エネルギー密度
- 初期揺らぎスペクトラム: インフレーション理論の検証データ
- バリオン物理: 原始元素合成と整合する重元素比
- 幾何学: 宇宙の曲率と時空構造
- ニュートリノ: 軽いニュートリノの個数と質量
- 暗黒物質: 冷たい暗黒物質モデルの検証
これらの情報は、CMBの温度分布を詳細に解析することで抽出されます。
CMBの角度パワースペクトラムは、球面調和関数展開の係数の分散として定義されます。多重極ℓに対するパワースペクトラムCℓは、物理的な密度揺らぎのフーリエモードと密接に関連しています。観測される主要な特徴には以下があります:
- 第一音響ピーク: ℓ ≈ 220(宇宙の幾何学を反映)
- 第二、第三音響ピーク: バリオン密度の精密測定
- 減衰領域: シルクダンピングによる小スケール減衰
- 偏光パターン: 原始重力波の探索
特に重要なのは、音響ピークの相対的な高さから、バリオン密度Ωbhと物質密度Ωmhの精密な値が決定できることです。現在の観測では、Ωbh² ≈ 0.02237、Ωmh² ≈ 0.1432という値が得られており、これらは他の独立な観測(原始元素合成、超新星観測など)と高い精度で一致しています。
最終散乱面の「厚み」も重要な観測量です。再結合は瞬間的な過程ではなく、有限の時間幅を持つため、最終散乱面には物理的な厚みがあります。この厚みは可視深度の変化率で特徴づけられ、小角度スケールでの温度揺らぎの減衰(シルクダンピング)として観測されます。
シルクダンピングの減衰スケールλSilkは、拡散距離として与えられます:
λSilk = ∫ (vs/Γ) dt
この積分は再結合期間中の音速と散乱頻度の変化を考慮したものです。観測されるダンピングスケールから、再結合期の物理過程を詳細に検証することができます。
現代宇宙論への影響
最終散乱面の物理は、現代宇宙論の基盤となる標準模型の確立において決定的な役割を果たしました。CMBの発見とその詳細な観測により、以下の重要な宇宙論的概念が確立されました:
宇宙論的原理の検証: CMBの高い等方性は、宇宙の大規模均質性を示す強力な証拠となりました。温度の方向依存性は10⁻⁵のレベルでしか存在せず、これは宇宙論的原理を強く支持しています。
インフレーション理論の観測的基盤: CMBの温度揺らぎスペクトラムは、インフレーション期に生成された量子揺らぎの特徴と一致します。特に、揺らぎの統計的性質やスケール不変性は、単一場インフレーションモデルの予想と良く合致しています。
暗黒物質の存在証明: バリオン音響振動の解析から、通常物質(バリオン)だけでは観測される構造を説明できないことが明確になりました。CMBデータは、冷たい暗黒物質の存在を強く示唆する証拠を提供しています。
宇宙年齢の精密決定: 最終散乱面における物理条件の解析により、宇宙年齢は137.7億年という高精度で決定されました。この値は、最古の星の年齢測定や放射性元素の崩壊時間と整合しています。
最終散乱面の物理は、将来の宇宙論研究においても中心的な役割を果たし続けると予想されます:
- 原始重力波探索: インフレーション期の重力波は、CMBのB偏光パターンとして観測される可能性があります
- 暗黒エネルギー研究: 後期宇宙の観測とCMBデータの結合により、暗黒エネルギーの性質解明が進展します
- ニュートリノ質量: CMBの小角度構造から、ニュートリノ質量の上限値がさらに精密化されます
- 新物理探索: 標準模型を超える新しい物理の痕跡が、CMBの微細構造に現れる可能性があります
現在進行中の地上・宇宙ベースの観測プロジェクトは、これまでよりもさらに高精度でCMBを測定し、最終散乱面の物理をより深く理解することを目指しています。これらの研究は、宇宙の起源と進化、そして物理学の基本法則そのものに関する理解を、さらに深いレベルへと導いていくことでしょう。
最終散乱面の研究は、単に過去の出来事を調べるだけでなく、宇宙の未来や物理学の統一理論に関する重要な手がかりを提供し続けています。この小さな温度揺らぎから読み取れる情報の豊富さと精密さは、現代物理学の最も美しい成果の一つと言えるでしょう。