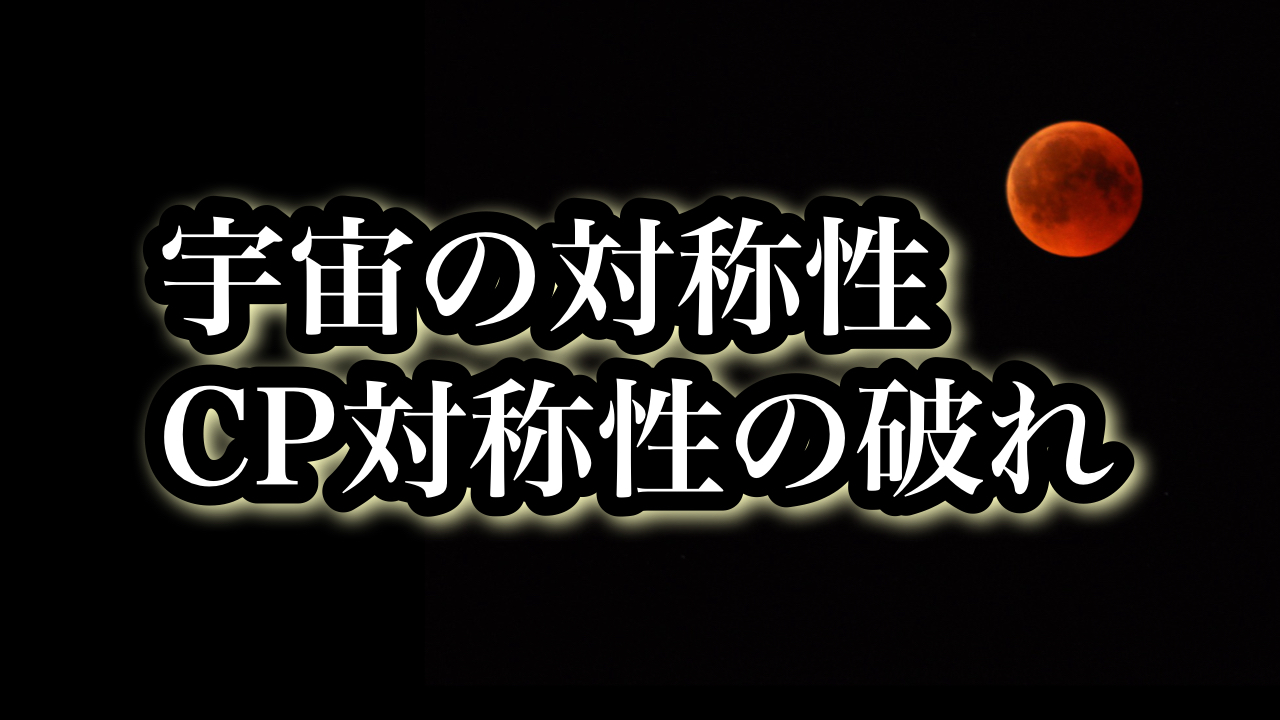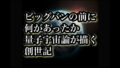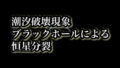目次
宇宙最大の謎:物質と反物質の非対称性
私たちが住むこの宇宙には、驚くべき謎が存在します。それは「なぜ宇宙は物質で満たされているのか」という根本的な問いです。現代物理学の理論によれば、ビッグバンの瞬間、物質と反物質は等量で生成されたはずでした。しかし、もしそれが真実であれば、物質と反物質は互いに対消滅し、宇宙には光子しか残らなかったでしょう。ところが現実の宇宙には、銀河や星、惑星、そして私たち人間を構成する物質が圧倒的に存在しています。
この謎を解く鍵となるのが「CP対称性の破れ」という現象です。CP対称性とは、粒子を反粒子に置き換え(C:電荷共役変換)、さらに空間座標を反転させる(P:パリティ変換)という二つの操作を同時に行っても物理法則が変わらないという対称性を指します。もしCP対称性が完全に保たれていれば、物質と反物質の振る舞いは完全に対称であり、現在の宇宙の姿を説明することはできません。
観測によれば、宇宙全体で物質は反物質に対して約十億分の一だけ多く存在しています。つまり、十億個の反粒子に対して十億と一個の粒子が存在したことになります。この極めてわずかな非対称性こそが、現在の宇宙を形作る物質の起源なのです。この微細な違いがなければ、私たちも、地球も、太陽も存在し得なかったのです。
対称性とは何か:自然界の美しい法則
物理学において対称性は極めて重要な概念です。対称性とは、ある変換を施しても系の性質が変わらないことを意味します。例えば、雪の結晶は回転させても同じ形に見えるという回転対称性を持っています。自然界の基本法則も様々な対称性を持ち、これらの対称性から保存則が導かれることが知られています。
時間並進対称性からはエネルギー保存則が、空間並進対称性からは運動量保存則が、回転対称性からは角運動量保存則が導かれます。これらの対称性と保存則の関係は、ネーターの定理として数学的に厳密に定式化されており、現代物理学の根幹をなしています。
素粒子物理学では、さらに特殊な対称性が議論されます。その一つが電荷共役対称性(C対称性)です。これは粒子を反粒子に置き換えても物理法則が変わらないという対称性です。電子を陽電子に、陽子を反陽子に置き換えても、それらの相互作用は同じ法則に従うはずだという考え方です。
もう一つの重要な対称性がパリティ対称性(P対称性)です。これは空間座標を反転させる、つまり鏡像世界を考えたときに物理法則が変わらないという対称性です。右手系と左手系を入れ替えても、自然法則は同じであるという主張です。
長い間、物理学者たちはこれらの対称性が基本的な自然法則において完全に保たれていると信じていました。しかし、二十世紀半ばになって、この常識は覆されることになります。一九五六年、リーとヤンは弱い相互作用においてパリティ対称性が破れている可能性を理論的に提案しました。翌年、ウーの実験グループがコバルト六十の崩壊実験によってこれを実証し、物理学界に衝撃を与えました。
CP対称性の破れの発見
パリティ対称性の破れが発見された後、物理学者たちはC対称性とP対称性を組み合わせたCP対称性なら保たれているのではないかと考えました。確かに、粒子を反粒子に置き換え、かつ鏡像世界を考えれば、対称性は回復されるように思えました。弱い相互作用はP対称性を破るけれども、CP対称性は保たれているという見方が有力になったのです。
ところが一九六四年、クロニンとフィッチの実験グループが中性K中間子の崩壊を詳細に調べた結果、CP対称性もまた破れていることを発見しました。これは物理学の歴史における画期的な発見でした。この功績により、クロニンとフィッチは一九八○年にノーベル物理学賞を受賞しています。
中性K中間子には、K0とその反粒子である反K0という二つの状態があります。これらは互いに混合して、寿命の短いKS中間子と寿命の長いKL中間子という二つの状態を作ります。CP対称性が完全に保たれていれば、KL中間子は二つのパイ中間子には崩壊できないはずでした。しかし実験の結果、千分の一程度の確率でこの禁止されたはずの崩壊が起こることが確認されたのです。
この発見は、自然界の基本法則が物質と反物質を完全には対称に扱っていないことを示す決定的な証拠でした。CP対称性の破れは極めて小さな効果ですが、宇宙の進化において決定的な役割を果たしました。この小さな非対称性が、ビッグバン直後の高温高密度の環境において、物質が反物質よりもわずかに多く生成される原因となったのです。
サハロフの三条件
一九六七年、ソビエト連邦の物理学者アンドレイ・サハロフは、宇宙における物質優勢を説明するための三つの必要条件を提唱しました。これらは「サハロフの三条件」として知られ、バリオン数生成(宇宙の物質・反物質非対称性の起源)を理解する上での基盤となっています。
第一の条件は、バリオン数を破る相互作用の存在です。バリオン数とは、陽子や中性子などのバリオンの数から反バリオンの数を引いたもので、通常の相互作用では保存されます。しかし、宇宙初期に物質が反物質よりも多く生成されるためには、バリオン数が変化する過程が必要です。標準模型では厳密にはバリオン数保存則は成り立っておらず、非摂動的な過程であるスファレロン過程などでバリオン数が破れることが知られています。
第二の条件は、C対称性とCP対称性の破れです。もしこれらの対称性が完全に保たれていれば、物質を生成する過程と反物質を生成する過程の確率は等しく、結果として物質と反物質は同量生成されることになります。CP対称性の破れがあって初めて、物質の生成が反物質の生成よりも優位になる可能性が生まれるのです。
第三の条件は、熱平衡からのずれです。熱平衡状態では、詳細釣り合いの原理により、ある過程とその逆過程の速度は等しくなります。これではバリオン数の非対称性は蓄積されません。宇宙の膨張や相転移などによって系が熱平衡から外れることで、生成された非対称性が保持されるのです。
これら三つの条件が同時に満たされることで、初めて宇宙における物質優勢が実現可能となります。現代の素粒子宇宙物理学では、これらの条件がどのように満たされたかを明らかにすることが重要な研究課題となっています。
標準模型におけるCP対称性の破れ
現在の素粒子物理学の基礎理論である標準模型は、CP対称性の破れを自然に含んでいます。標準模型では、クォークの質量を決めるメカニズムの中にCP対称性を破る項が現れます。これは小林・益川理論として知られ、一九七三年に小林誠と益川敏英によって提唱されました。
標準模型には六種類のクォークが存在します。アップ、ダウン、チャーム、ストレンジ、トップ、ボトムの六つです。これらのクォークは弱い相互作用を通じて互いに変換し合います。この変換を記述するのが小林・益川行列(CKM行列)と呼ばれる三行三列の複素行列です。
CKM行列が複素数の位相を持つことが、CP対称性の破れの源となります。クォークが三世代以上存在することで、この複素位相を消去できない形で理論に組み込まれます。実際、クォークが二世代しかない場合は、CKM行列を適切に再定義することで実数行列にすることができ、CP対称性は保たれます。しかし三世代になると、一つの消去できない複素位相が残り、これがCP対称性の破れを引き起こすのです。
この理論的予測は、その後の実験によって見事に検証されました。特にB中間子の崩壊を詳細に調べた実験により、小林・益川理論が予言するCP対称性の破れのパターンが確認されました。この功績により、小林誠と益川敏英は二○○八年にノーベル物理学賞を受賞しています。
標準模型の限界とバリオン数生成の課題
標準模型はCP対称性の破れを含んでいますが、残念ながら現在観測されている宇宙の物質優勢を十分に説明することはできません。小林・益川理論によるCP対称性の破れは確かに存在しますが、その大きさが宇宙のバリオン数非対称性を生み出すには小さすぎるのです。観測される物質と反物質の比率は、標準模型だけでは説明できない大きさであることが計算から明らかになっています。
さらに標準模型には、サハロフの第一条件であるバリオン数を破る相互作用についても問題があります。標準模型ではスファレロン過程と呼ばれる非摂動的な過程でバリオン数が破れますが、この過程が十分に働くためには、電弱相転移が一次相転移である必要があります。しかし現在のヒッグス粒子の質量の値から判断すると、実際の電弱相転移は二次相転移またはクロスオーバーであり、熱平衡からの十分なずれが得られません。
これらの理由から、宇宙のバリオン数非対称性を説明するためには、標準模型を超えた新しい物理が必要だと考えられています。新しい粒子、新しい相互作用、あるいは新しい対称性の破れのメカニズムが、初期宇宙において重要な役割を果たしたと推測されているのです。この「標準模型を超えた物理」の探求が、現代の素粒子宇宙物理学における最重要課題の一つとなっています。
バリオン数生成のシナリオ
宇宙における物質優勢を説明するため、物理学者たちは様々なバリオン数生成のシナリオを提案してきました。これらのシナリオは、宇宙のどの時期にバリオン数非対称性が生成されたかによって分類することができます。それぞれのシナリオは異なる新物理を必要とし、異なる観測的な予言を与えます。
大統一理論に基づくバリオン数生成は、最も古典的なシナリオの一つです。このシナリオでは、宇宙誕生直後の極めて高温の時期に、重い粒子の崩壊を通じてバリオン数が生成されます。大統一理論では、クォークとレプトンを統一的に扱い、バリオン数とレプトン数を破る相互作用が自然に現れます。温度が大統一スケール(約十の十五乗ギガ電子ボルト)から下がる過程で、重い粒子が崩壊し、その際にCP対称性の破れによって粒子と反粒子の生成率にわずかな差が生じます。
電弱バリオン数生成は、より低いエネルギースケールで起こるシナリオです。宇宙の温度が電弱スケール(約百ギガ電子ボルト)まで下がったときに起こる電弱相転移の際に、バリオン数が生成されるというものです。このシナリオでは、相転移によって生じる泡の壁の中で、スファレロン過程とCP対称性を破る相互作用が組み合わさってバリオン数が生成されます。ただし、このシナリオが働くためには標準模型を超えた新しいCP対称性の破れの源が必要です。
アフレック・ダインメカニズムは、超対称性理論の枠組みで提案されたシナリオです。このメカニズムでは、スカラー場が持つ大きな初期値が、宇宙膨張に伴って振動しながら減衰する過程でバリオン数が生成されます。超対称性理論に現れる平坦な方向に沿って、スカラー場が大きな値を持つことができ、その後の進化でCP対称性の破れを通じてバリオン数非対称性が蓄積されます。
レプトジェネシスという革新的アプローチ
近年、特に注目を集めているのがレプトジェネシスと呼ばれるシナリオです。これは一九八六年に福来正孝によって提唱され、その後多くの研究者によって発展させられてきました。レプトジェネシスの基本的なアイデアは、まずレプトン数の非対称性を生成し、それをスファレロン過程によってバリオン数の非対称性に変換するというものです。
このシナリオで重要な役割を果たすのが、重いニュートリノです。標準模型のニュートリノは質量を持たないとされていましたが、一九九八年のスーパーカミオカンデによるニュートリノ振動の発見により、ニュートリノが小さいながらも質量を持つことが確立されました。この質量を説明する最も自然な方法は、シーソー機構と呼ばれるメカニズムです。
シーソー機構では、標準模型の軽いニュートリノに加えて、非常に重い右巻きニュートリノが存在すると仮定します。この重いニュートリノと軽いニュートリノが混合することで、観測される軽いニュートリノの質量が自然に小さくなります。ちょうどシーソーの一方が上がると他方が下がるように、一方のニュートリノが非常に重ければ、もう一方は非常に軽くなるのです。
レプトジェネシスのシナリオでは、この重い右巻きニュートリノが初期宇宙において熱的に生成され、その後崩壊します。この崩壊過程においてCP対称性の破れがあると、レプトンと反レプトンの生成率に差が生じます。具体的には、重いニュートリノがレプトンとヒッグス粒子に崩壊する確率と、反レプトンとヒッグス粒子に崩壊する確率がわずかに異なるのです。
生成されたレプトン数の非対称性は、その後の宇宙の進化において重要な役割を果たします。宇宙の温度が電弱スケール程度まで下がると、スファレロン過程が活発に働き始めます。この過程はバリオン数とレプトン数を変換する性質を持っているため、レプトン数の非対称性の一部がバリオン数の非対称性に変換されます。この変換の比率は、標準模型の粒子の種類から計算することができ、観測されるバリオン数非対称性を再現できることが示されています。
レプトジェネシスの魅力的な点は、複数の観測事実を統一的に説明できることです:
- ニュートリノ質量の起源
- 宇宙のバリオン数非対称性の起源
- 大統一理論スケールより低いエネルギーでの実現可能性
- 重力波観測などによる将来的な検証可能性
このシナリオでは、重いニュートリノの質量スケールが十の十乗から十の十五乗ギガ電子ボルト程度であると予想されています。このエネルギースケールは、直接の加速器実験では到達困難ですが、宇宙論的観測や精密測定の進展により、間接的な検証が可能になりつつあります。
標準模型を超えた物理理論
バリオン数生成を説明するために提案されている標準模型を超えた理論には、様々なものがあります。これらの理論は、単にバリオン数生成だけでなく、暗黒物質や重力の量子化など、標準模型が抱える他の問題も解決することを目指しています。
超対称性理論は、最も広く研究されている標準模型の拡張です。この理論では、すべてのフェルミオンに対応するボソンパートナーが、すべてのボソンに対応するフェルミオンパートナーが存在します。超対称性理論は、ヒッグス粒子の質量の安定性の問題を解決し、大統一理論との整合性を改善し、暗黒物質の候補を自然に提供します。またCP対称性の破れの新しい源も含んでおり、バリオン数生成のシナリオを豊かにします。
余剰次元理論も興味深い可能性を提供します。私たちが通常経験する三次元空間に加えて、コンパクト化された余剰次元が存在するという考え方です。このような理論では、重力が他の力よりも弱い理由や、階層性問題と呼ばれる素粒子物理学の難問を説明できる可能性があります。余剰次元の構造によっては、新しいCP対称性の破れの機構も現れ得ます。
大統一理論は、強い力、弱い力、電磁気力という三つの力を統一的に記述しようとする理論です。十分に高いエネルギーでは、これらの力が一つの力として振る舞うと予言します。大統一理論では、クォークとレプトンが統一的に扱われ、バリオン数とレプトン数を破る相互作用が自然に現れます。これはバリオン数生成のメカニズムを提供すると同時に、陽子崩壊という劇的な予言も与えます。
これらの理論はいずれも実験的検証を待っている段階ですが、将来の加速器実験や宇宙観測によって、その正しさが試されることになるでしょう。バリオン数生成の謎を解くことは、これらの新しい物理理論への重要な手がかりとなると期待されています。
実験による検証と観測的証拠
CP対称性の破れとバリオン数生成の理論を検証するため、世界中で様々な実験が行われています。これらの実験は、加速器を用いた高エネルギー実験から、宇宙線観測、さらには宇宙マイクロ波背景放射の精密測定まで、多岐にわたります。それぞれの実験が、この宇宙の根源的な謎に迫る重要な手がかりを提供しています。
高エネルギー加速器実験では、B中間子やD中間子などの重いクォークを含む粒子の崩壊を詳細に調べることで、CP対称性の破れの性質を明らかにしています。特に日本の高エネルギー加速器研究機構(KEK)のBelle実験と、欧州原子核研究機構(CERN)のLHCb実験は、世界最高精度でCP対称性の破れを測定してきました。これらの実験では、B中間子が様々な粒子に崩壊する際の確率を精密に測定し、粒子と反粒子の崩壊の違いを検出しています。
Belle実験は二○○一年から二○一○年にかけて稼働し、B中間子のCP対称性の破れを確認しました。その後継機であるBelle II実験は二○一九年から本格的なデータ収集を開始し、さらに高い精度での測定を進めています。これらの実験データは、小林・益川理論の予言と驚くべき一致を示していますが、同時に標準模型を超えた新しい物理の兆候を探す試みも続けられています。
ニュートリノ実験も、バリオン数生成の謎を解く重要な鍵を握っています。日本のスーパーカミオカンデや、アメリカのNOvA実験、さらに建設中のハイパーカミオカンデなどが、ニュートリノ振動の精密測定を通じてCP対称性の破れを探索しています。ニュートリノセクターでのCP対称性の破れは、レプトジェネシスのシナリオと直接関係する可能性があり、重要な研究対象となっています。
最近の注目すべき成果として、T2K実験やNOvA実験が報告したニュートリノ振動におけるCP対称性の破れの兆候があります。これらの実験では、ニュートリノが反ニュートリノとは異なる振動パターンを示す可能性が観測されています。ただし統計的な有意性はまだ十分ではなく、より多くのデータ収集が必要とされています。ハイパーカミオカンデが完成すれば、この問題に決定的な答えを出せると期待されています。
宇宙論的観測もまた、バリオン数生成の理解に貢献しています。宇宙マイクロ波背景放射の精密観測により、宇宙におけるバリオンと光子の数の比が高精度で測定されています。プランク衛星による最新の観測では、この比が約六十億分の一であることが確認されており、これは理論的予言と比較するための基準となっています。
宇宙における物質分布の観測
宇宙における物質と反物質の分布についても、様々な観測が行われています。もし宇宙のどこかに大量の反物質が存在すれば、物質との境界で対消滅反応が起こり、特徴的なガンマ線が放出されるはずです。しかし、これまでの観測ではそのような大規模な対消滅の証拠は見つかっていません。これは、少なくとも観測可能な宇宙の範囲内では、物質が圧倒的に優勢であることを示しています。
国際宇宙ステーションに設置されたアルファ磁気分光器(AMS)は、宇宙線の中に含まれる反粒子を探索しています。これまでに反陽子や陽電子は検出されていますが、その量は物質粒子に比べて極めて少なく、また二次的な生成過程で説明可能な範囲内です。もし原始的な反物質領域が存在すれば、反ヘリウムや反炭素などのより重い反原子核が観測されるはずですが、現在まで決定的な証拠は得られていません。
ただし、二○一一年にAMSが捉えた数個の反ヘリウム候補イベントは、物理学界で議論を呼んでいます。これらが本当に反ヘリウムであれば、宇宙のどこかに反物質のドメインが存在する可能性を示唆します。しかし、信号が非常に弱く、バックグラウンドとの区別が難しいため、さらなる観測による確認が必要とされています。
銀河団や銀河間物質の分布からも、宇宙の大規模構造における物質優勢が確認されています。X線天文衛星による観測では、銀河団を満たす高温ガスの性質が詳しく調べられており、これらがすべて通常の物質から構成されていることが分かっています。もし反物質が存在すれば、その対消滅によって独特のスペクトルが観測されるはずですが、そのような証拠は見つかっていません。
重力波観測による新たな可能性
重力波天文学の発展は、バリオン数生成の研究に新しい窓を開きつつあります。重力波は時空の歪みが波として伝わる現象で、二○一五年にLIGOによって初めて直接観測されました。これまでに観測された重力波のほとんどは、ブラックホールや中性子星の合体によるものですが、初期宇宙で起こった相転移も重力波を生成する可能性があります。
もし電弱相転移が一次相転移として起こっていれば、そこで生成された重力波が現在まで残っている可能性があります。この原始重力波の観測は、電弱バリオン数生成のシナリオを検証する直接的な方法となります。将来の宇宙重力波望遠鏡LISAや、地上の第三世代重力波検出器Einstein Telescopeなどが、このような信号を捉えることができると期待されています。
レプトジェネシスのシナリオとの関連も注目されています。重いニュートリノの崩壊過程や、それに伴う宇宙の相転移が重力波信号を残す可能性が理論的に研究されています。もしそのような信号が検出されれば、レプトジェネシスのエネルギースケールや、CP対称性の破れの大きさについて重要な情報が得られるでしょう。
現在進行中の重力波観測プロジェクトには以下のようなものがあります:
- LIGO(アメリカ)とVirgo(イタリア):地上での観測を継続
- KAGRA(日本):低温技術を用いた新世代検出器
- LISA:宇宙空間での観測を目指す計画
- Einstein Telescope:地下に建設予定の超高感度検出器
- Cosmic Explorer:より長いアームを持つ次世代検出器の構想
これらの観測装置が稼働すれば、初期宇宙の物理過程について、これまでにない詳細な情報が得られると期待されています。
今後の展望と未解決問題
CP対称性の破れとバリオン数生成の研究は、依然として多くの未解決問題を抱えています。標準模型のCP対称性の破れだけでは宇宙の物質優勢を説明できないことは明らかですが、どのような新しい物理が必要なのかはまだ完全には分かっていません。複数のシナリオが提案されており、それぞれに長所と短所があります。
レプトジェネシスは現在最も有力なシナリオの一つですが、重いニュートリノの質量やCP対称性の破れの大きさなど、未知のパラメータが多く含まれています。これらのパラメータを実験的に制約することが、今後の重要な課題となっています。特に、軽いニュートリノの質量階層性やマヨラナ性の測定は、レプトジェネシスのシナリオを絞り込む上で決定的な情報を提供するでしょう。
ニュートリノを放出しない二重ベータ崩壊の探索も、重要な実験的挑戦です。もしこの過程が観測されれば、ニュートリノがマヨラナ粒子であること、つまり粒子と反粒子が同一であることが証明されます。これはレプトン数が破れていることの直接的な証拠となり、レプトジェネシスのシナリオを強く支持することになります。世界中で複数の実験グループが、より高感度な検出器の開発を進めています。
理論面でも多くの課題が残されています。標準模型を超えた理論は数多く提案されていますが、どれが正しいのかを決定するには至っていません。超対称性理論は長年有力視されてきましたが、LHC実験でこれまでのところ超対称性粒子の証拠が見つかっていないことから、その存在に疑問符が付けられています。一方で、余剰次元理論や複合ヒッグスモデルなど、他の可能性も活発に研究されています。
暗黒物質との関連も興味深い研究テーマです。宇宙には通常物質の約五倍の暗黒物質が存在することが分かっていますが、その正体は未だ不明です。いくつかの理論では、バリオン数生成と暗黒物質生成が関連している可能性が示唆されています。例えば、アシンメトリック暗黒物質モデルでは、バリオン数非対称性と暗黒物質の量が同じ起源から説明されます。
将来の実験計画と観測プロジェクトは、これらの謎に答えを出すことを目指しています:
- ハイパーカミオカンデによるニュートリノCP対称性の精密測定
- 国際リニアコライダー(ILC)による新粒子探索
- 次世代宇宙望遠鏡による原始重力波の観測
- より高感度な二重ベータ崩壊実験
- 高精度フレーバー物理実験による新物理の間接探索
宇宙の物質優勢という謎は、素粒子物理学と宇宙論が交差する最も深遠な問題の一つです。その解明は、自然界の基本法則についての私たちの理解を根本から変える可能性を秘めています。CP対称性の破れの研究は、単なる学問的興味を超えて、私たちの存在そのものの起源に関わる問いに答えようとする試みなのです。今後数十年の間に、実験技術の進歩と理論的洞察の深化により、この宇宙最大の謎の一つが解き明かされることを期待したいと思います。